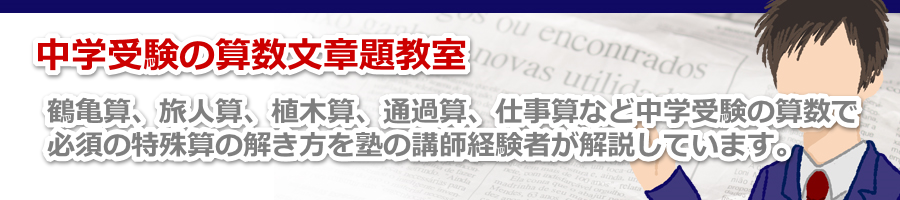
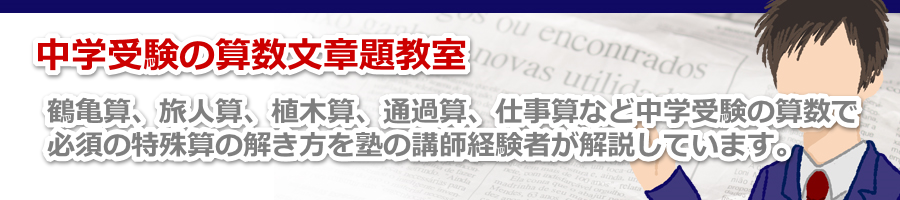
金額が出てくる和差算の解き方
中学受験の算数に出てくる和差算についての解き方の解説です。
和差算というのは、大小二つの数字の和(足した数字)と差(大きい数から小さい数を引いた数字)がわかれば、それぞれの数字がいくつかわかるというものです。
中学受験では単独で出題されるよりも、他の文章題との組み合わせで出ることが多い問題です。まずは、基本となる金額が出てくる問題を見ていきます。

【金額の和差算問題】
はるかさんと弟の一か月のおこづかいを足すと1,800円になります。はるかさんが弟より200円多くおこづかいをもらっているとすると、二人のそれぞれのおこづかいはいくらでしょうか?
これが最も基本的な和差算の問題です。
問題文から和と差を整理してみましょう。
和とは、数字を足すこと、差とは、数字を引くことです。
- 和…1,800円
- 差…200円
「はるかさんが弟より200円多くおこづかいをもらっている」ということは、はるかさんのおこづかいから弟のおこづかいを引いた金額が200円になるということです。
和差算の差は大きい数字から小さい数字を引いた値のことです。
文章に出てくる順番は関係ありません。
では、解き方を見ていきます。
金額が出てくる和差算の解き方
和差算には公式があります。
【和差算の公式】
- 大きいほうの数 = (和+差)÷2
- 小さいほうの数 = (和−差)÷2
これをあてはめて解いていけばカンタンです。
上記の問題では「和」…1,800円、「差」…200円なので、
- 大きいほうの数 = (1,800+200)÷2
- 小さいほうの数 = (1,800−200)÷2
計算すると
- 大きいほうの数 = 1,000
- 小さいほうの数 = 800
となります。
大きいほうの数(1,000)というのは「はるかさんのおこづかいの金額」、小さいほうの数(800)が「弟の金額」です。
問題文で確認してみましょう
「はるかさんと弟の一か月のおこづかいを足すと1,800円になります。」
- はるかさんのおこづかい…1000円
- 弟のおこづかい…800円
- 足すと1800円
あってますね。
「はるかさんが弟より200円多くおこづかいをもらっている」
- はるかさんのおこづかい…1000円
- 弟のおこづかい…800円
- はるかさんのほうが200円の多い
これもあってますね。
答え.はるかさん…1,000円、弟…800円
金額が出てくる和差算の解き方(2)
もう一問、別の問題で見てみましょう。
【金額の和差算問題(2)】
お父さんとお母さんのお昼のご飯代を足すと1500円になります。お母さんのほうがお父さんより300円高いとすると、2人のお昼代はそれぞれいくらでしょうか?
まずは和と差を整理します。
和…1500円、差…300円ですね。
これを公式にあてはめます。
大きいほうの数字でも小さいほうの数字でもどちらかを求めればOKです。
では、大きいほうの数字で公式にあてはめてみます。
【和差算の公式】
- 大きいほうの数 = (和+差)÷2
和…1500円、差…300円なので、和+差=1800円。
これを2で割るので、900円が大きいほうの数字です。
問題文には「お母さんのほうがお父さんより300円高い」とあります。
ということは、お母さんが大きいほうの数字900円になります。
すると、お父さんはお母さんより300円少ないので900−300=600円となります。
答え.お父さん600円、お母さん900円
和差算の練習問題
けんご君と妹の身長を足すと260cmになります。けんご君が妹より40cm身長が高いとすると、二人のそれぞれの身長は何cmでしょうか?
正解・解説を表示
この問題の和と差を整理します。
- 和…260
- 差…40
あとは和差算の公式にあてはめます。
【和差算の公式】
- 大きいほうの数 = (和+差)÷2
- 小さいほうの数 = (和−差)÷2
公式に当てはめて計算すると…
- 大きいほうの数 = (260+40)÷2 = 150
- 小さいほうの数 = (260−40)÷2 = 110
確認してみると、
足して260(150+110)、差が40(150−110)であっています。
答え.けんご君150cm、妹110cm



