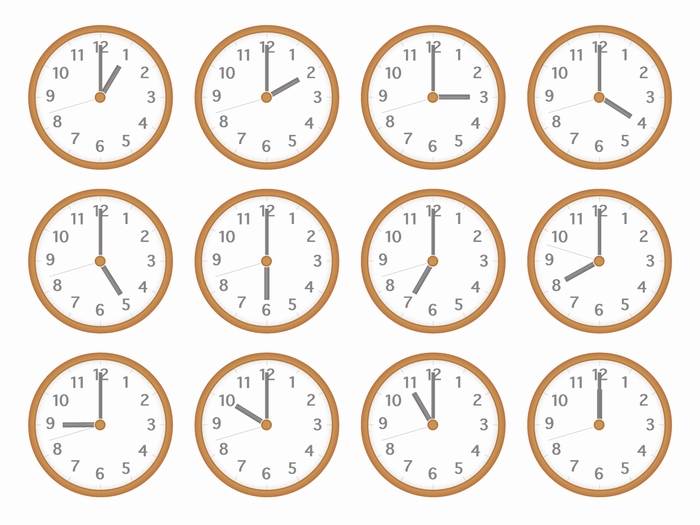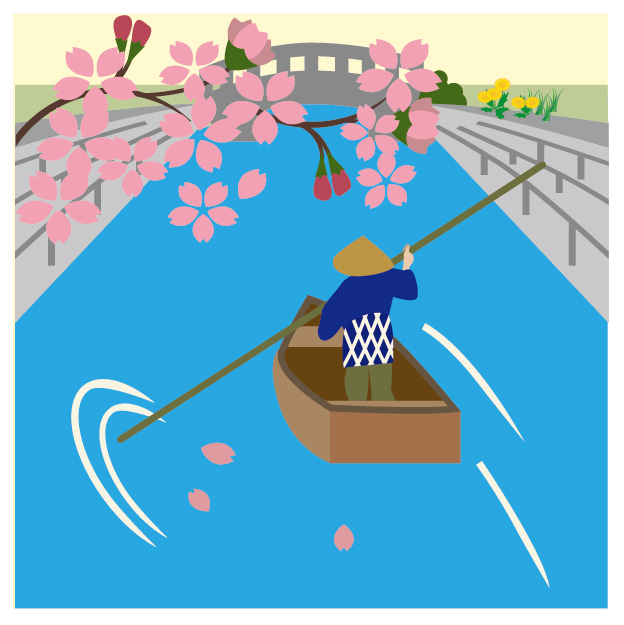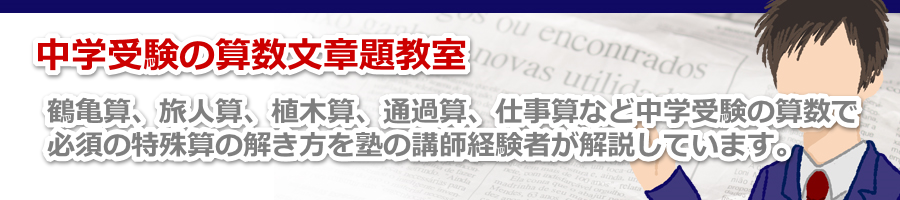
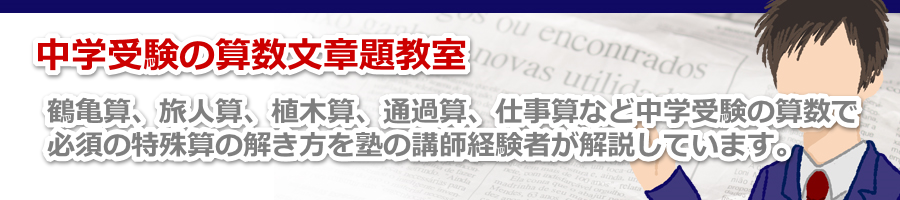
流水算を解くための必須用語(静水、川を上る、川を下る)

流水算を解くためには算数だけでなく国語の知識が必須です。具体的に言えば、「静水」「川を上る」「川を下る」といった流水算に出てくる用語の意味を正しく理解している必要があります。
「静水」など日常会話では使うことのない用語が出てくると、それだけで問題が難しい、できないと感じてしまうものです。しっかり、用語を覚えておきましょう。
流水算での静水とは?
流水算の問題では次のように「静水」という言葉が出てきます。
静水時の速さが時速10kmの船が…
静水(せいすい)を辞書で引くと、「静止している水」という意味が出てきますが、川の水が静止しているというのはイメージできないですよね。川の水はつねに流れていますし…。
流水算での静水というのは、「水の流れを無視した」という意味です。
なので、静水時とは「水の流れを無視したとき」ということになります。
つまり、『静水時の速さが時速10kmの船が…』という文章は、『水の流れを無視した(水の流れが関係ない)ときの速さが時速10km…』という意味になります。
このように船が本来持っているスピードを表すときに、静水時の速さという言い方をするのです。これに川の流れの速さが加わるのが流水算のポイントです。
川を上る、川を下る
もうひとつ、流水算で大事な用語は「川を上る」と「川を下る」です。
- 「川を上る」…川の流れと反対方向に進むこと
- 「川を下る」…川の流れと同じ方向に進むこと
川の上流から下流に進むことは、川を下る。川の下流から上流に進むことは、川を上るです。上流に向かうから上る、下流に向かうから下るです。
川の上流とは川が流れ出すほう、下流は川が流れてくる(流れつく)ほうのことです。
流水算では、船が川を上るのか下るのかによって速さが変化します。
- 船が川を上る場合の速さ = 船の速さ − 川の流れの速さ
- 船が川を下る場合の速さ = 船の速さ + 川の流れの速さ
船が川を上るということは、川の流れと反対方向に進むので、川の水で押し戻される分だけ本来の(静水時の)船の速さよりも遅くなります。
反対に船が川を下るということは、川の流れと同じ方向に進むので、川の水の流れで進む分も加わり、本来の(静水時の)船の速さよりも速くなります。
「静水」、「川を上る」、」川を下る」は流水算でよく出てくる用語です。
正確に覚えておきましょう。