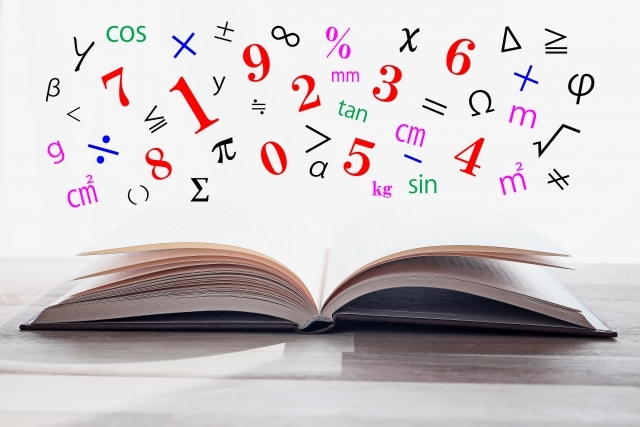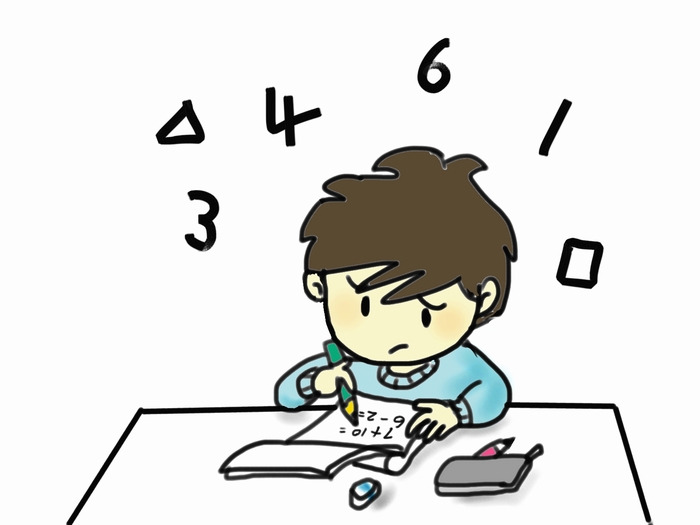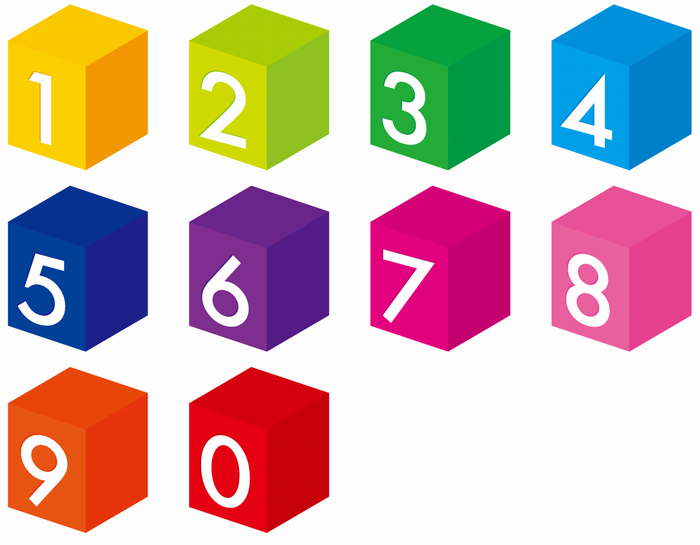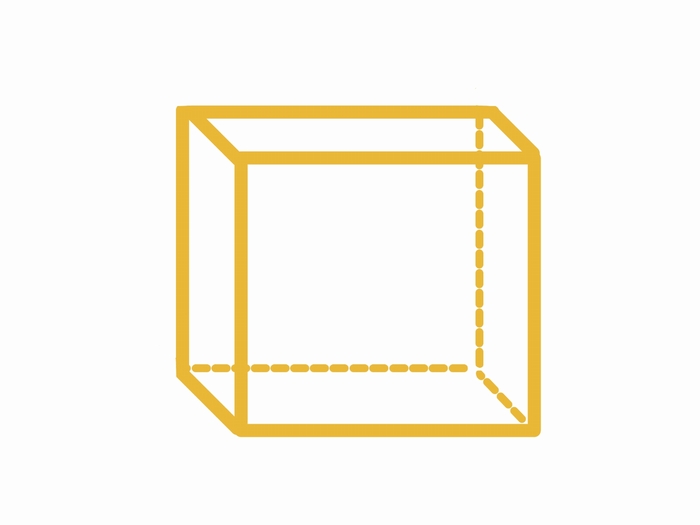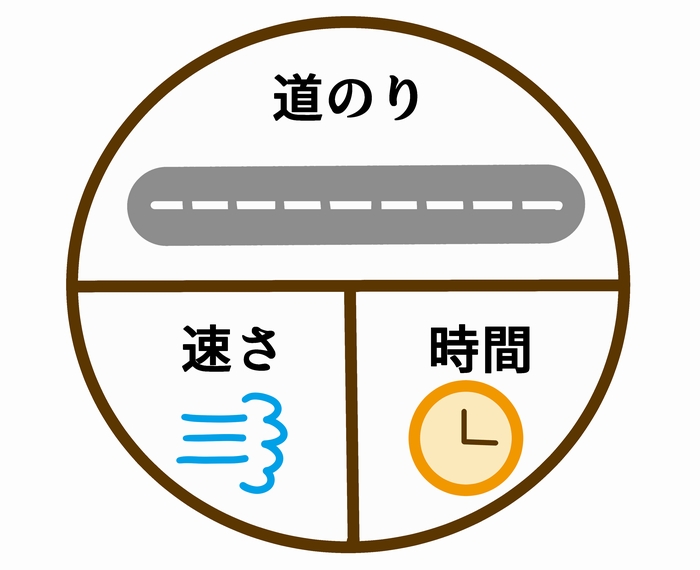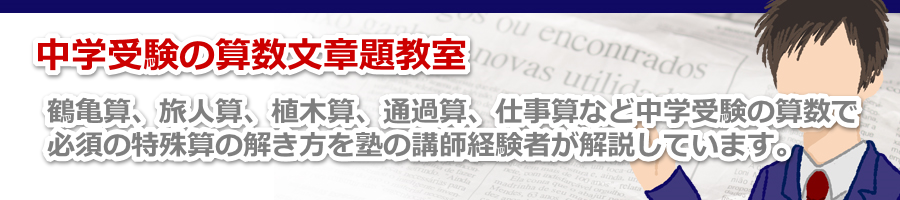
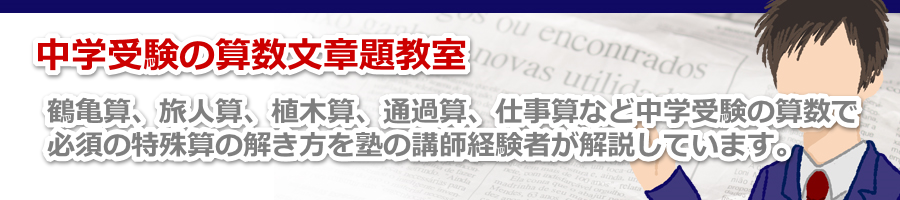
算数の文章題が苦手な人はココに気をつける

算数の文章題が苦手な人に共通するのが「問題の意味がわからない」ということです。
解き方がわからないのではなく、問題で何を問われているのかがわからないということです。
こうした場合、いくら解き方を勉強しても意味がありません。
何を求めれば良いのかがわかっていないと、応用が利かないからです。
そもそも、なぜ問題の意味が分からないのでしょうか?
言葉の意味がわからないことが原因
問題の意味がわからない原因は、問題文に使われている言葉の意味がわからないことがほとんどです。慣れていない言葉が多いのでピンとこないというのが正確かもしれません。
例えば、「単位あたり」。
算数が苦手な人は、問題文の中にこの言葉が出てきただけで、拒否反応というか、反射的に「わからない!」と思ってしまうことが少なくありません。
「単位あたり」なんて、日常生活では使わない言葉ですよね。
小学生にとっては算数の授業でしか出てこない言葉です。
ほかにも割り算が苦手な子にとっては「あまり」という言葉もクセモノです。
「あまりを求めなさい」という文章に引っかかってしまいます。
「あまり」は日常生活でも使われる言葉ですが、こうした言葉でも小学生にとってはピンとこないこともあります。「あまり」よりも「のこり」のほうがピンとくるかもしれません。
「あまり」を「のこり」に読み替えるように自分にとってピンとくる言葉に置き換えてみることが苦手克服への第一歩になります。
そのために必要な勉強は国語。
たくさんの言葉を知ることで自分にとってピンと来るものを探すことができます。
算数が苦手なことを克服するのに国語を勉強する。
意外に感じるかもしれませんが、これが効果的です。
文章題の意味がわからないという人は挑戦してみてください。
答えを丸写しする勉強法
文章題の意味がわかるようになったら、次には文章題の答えを丸写ししましょう。
丸写しするのは最終的な答えだけではありません、答えにたどり着くまでの式もです。
このときに大切なのは出来るだけ式の部分や解説の部分の答えが詳しく載っている問題集や参考書を使うことです。
最初は問題を解こうとする必要はありません。
「とりあえず5分間は頑張って考えてみる」といった努力も不要。
問題文を読んだら、すぐに答えの部分も丸写ししましょう。
このときに、なぜその式になるのかを考えます。
ヒントとなる説明があるはずなので、それを理解して式を写しましょう。
そうすることで文章題から式を導き出す能力が身につきます。
同じものを3回は書き写す
同じものを少なくとも3回は書き写すことで解き方も身についてくるようになります。3回繰り返す時間を確保するために、最初に問題を考える時間をなくしているのです。
逆に言えば、問題文を見てすぐに回答を丸写しするだけなので、3回写すぐらいの時間は十分にあるはずです。
何も考えずに1回写すだけでは何も身につきません。
同じものを3回は写しましょう。
そうすることで、文章題の問題を解くリズムというものがわかってきます。
どんな式を立てればいいのかも見えてくるものです。
回答を写しているときに、多少はわからないところがあってもかまいません。
くりかえし写しているとわからなかったところも、そのうちにわかってきます。
算数が苦手な人でもできる勉強法ですので、文章題で困っているのであれば試してみてください。