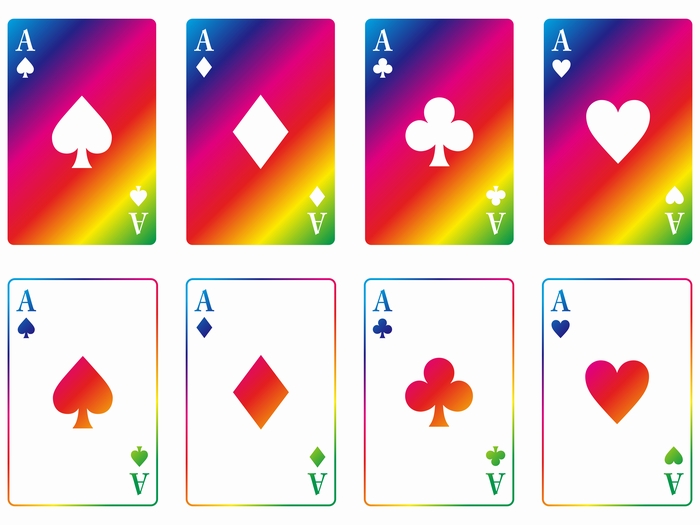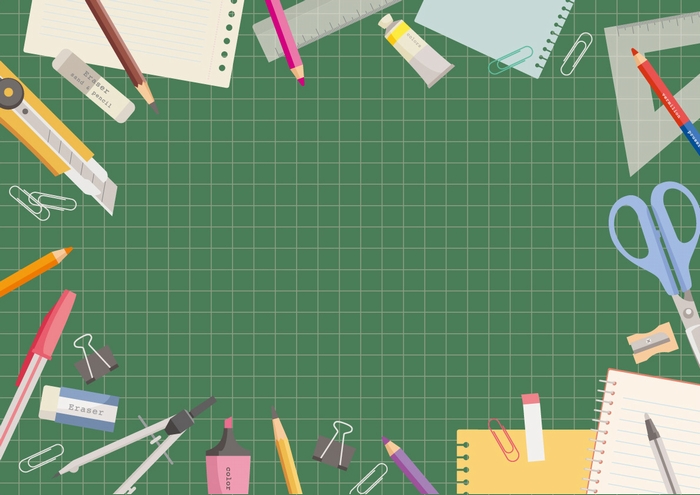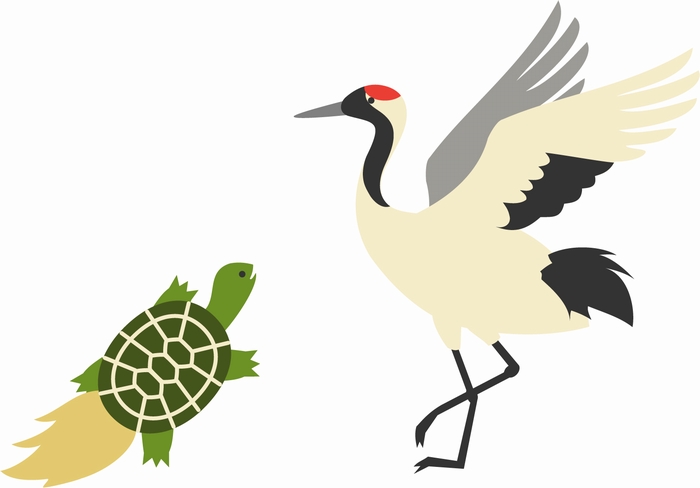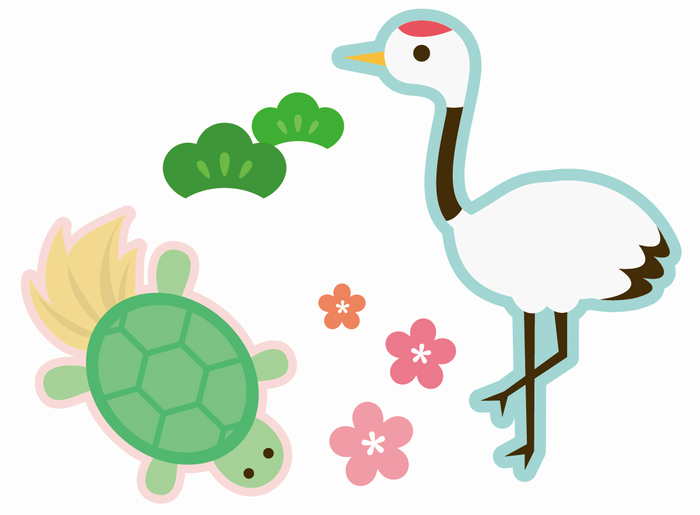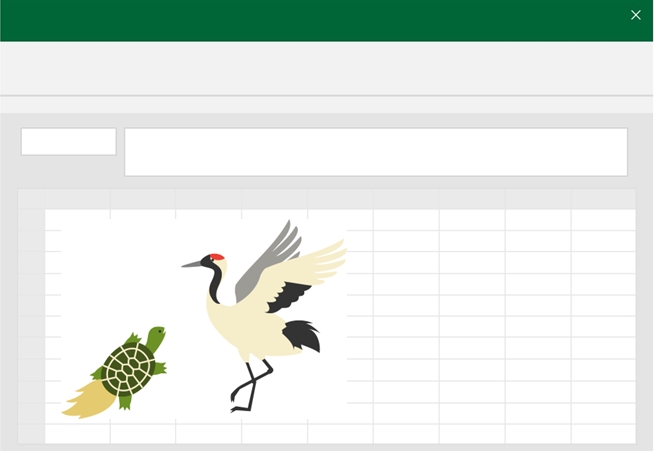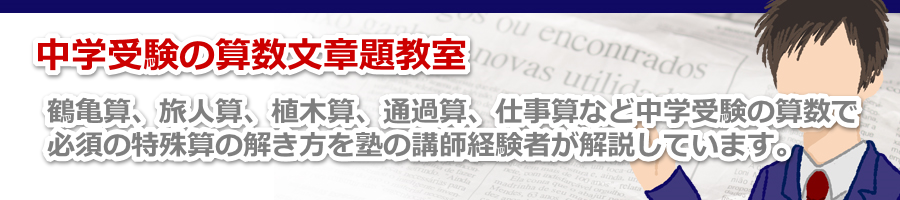
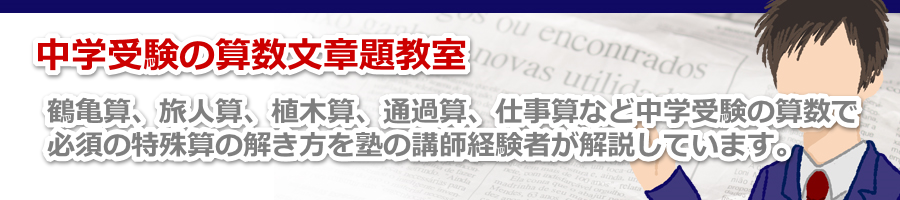
つるかめ算(速さの問題)の考え方と解き方

つるかめ算の考え方を使って解く速さの問題の解き方を解説します。
【つるかめ算(速さの問題)】
自転車と徒歩で自宅から駅まで行きました。自転車は分速150m、徒歩は分速60mの速さでした。自宅から駅までの距離は2040mで、16分で着きました。自転車に乗ったのは何分間だったでしょうか?
上の問題文では自転車と徒歩ですが、速さのちがう2種類のものが出てくるのなら考え方(解き方)は同じです。車と電車、走ってる人と歩いている人、歩くスピードがちがう2人など。
このスピードのちがいは、つるかめ算でいえば、ツルとカメの足の本数のちがいと同じ意味を持ちます。
- ツル…足2本(1羽あたり)
- カメ…足4本(1匹あたり)
これが上の問題文では次のようになります。
- 自転車…150m(分速)
- 徒 歩… 60m(分速)
さらに、つるかめ算に例えると、自宅からの駅までの距離は合計の足の数、自宅から駅までかかった時間が合計の頭数です。
- 自宅から駅までの距離(2040m)→つるかめ算だと足の数
- 自宅から駅までの時間(16分)→つるかめ算だと頭の数
表にして整理してみます。
| 上の問題 | つるかめ算 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
つるかめ算と同じように解く
つるかめ算の解き方は、すべてがどちらかだったらと考えて解くことです。
(例.すべてがカメだったら、足の本数と頭の数がどうなるか考える)
速さの問題もこれと同じように考えます。
すべてが自転車だったらどうなるでしょうか?
自転車の速さは150m(分速)。
自宅から駅までの時間(16分)がすべて自転車だったときの距離を求めます。
150m×16分=2400m となります。
(つるかめ算で言えば、すべてカメだとして足の数を求めるのと同じ。)
ところが、実際には駅までの距離は2040mです。
2400m−2040m=360mだけ多いことになります。
自転車を徒歩に1分変えると…
ここで1分、自転車から徒歩に変えると距離はどうなるでしょうか?
150m−60m=90m だけ進める距離が短くなります。
(カメをツルに変えると足が2本減るというのと同じ考え方です。)
全部自転車だと360m多い。
1分変えると90m短くなる。
では、何分変えればいいのか?カンタンですよね。
360m÷90m=4分を徒歩にすればよい。
合計16分のうち4分が徒歩なので、
16−4=12分が自転車に乗っていた時間となります。
答え.12分
つるかめ算と同じ解き方だったことがわかりましたか?
理解できなかったら、動画授業などをチェックしてみてください。